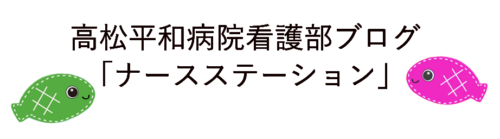緩和ケア病棟では、その時その時の一瞬を大切にし、大切なそのひとときを患者様ご家族に許可をいただいて写真に収めることをしています。
数多くある写真はどれも素敵な写真ですが、特に気に入っている写真が一枚あります。
それは患者様が口を大きく開いてハンバーガーを丸かじりで食べようとしているところで、その姿には「生」を感じます。
この写真を撮りA4サイズに印刷して患者様に届けると「また、変な写真撮って!」と言いながら二人で笑い転げました。
緩和ケアとは最期の時を過ごすイメージがあり、そのイメージのひとつに暗い感情のイメージがあるかと思います。
しかし、実際は穏やかな笑顔であったり、大声を出して笑ったりすることもあります。
この写真を撮った頃の患者様は、「私は人のお世話をすることが好きなの。それが役割だと思っている。でも、それも相手がいないとね・・・」「歩くことを大切にしているんだけど、いつかは歩けなくなるのよね」と、自身の役割を失う辛さや、近い将来に歩けなくなることへの辛さを話されていました。
私はそんな患者様の辛い思いに耳を傾けて傍に寄り添っていました。
 ある日、患者様より「今日は友人がハンバーガーを買ってきてくれるの」と嬉しそうに話されました。
ある日、患者様より「今日は友人がハンバーガーを買ってきてくれるの」と嬉しそうに話されました。
この患者様は本来とても明るく豪快に笑われ、ユーモアがある方でした。
そんな患者様だから私の思いが伝わるだろうと撮ったのが、紹介した写真になります。
私はこの写真に「今生きているあなたがとても大切です。あなたはどんな風に変わろうとも、あなたです。生きることを楽しむことができる強い人です」と思いを込めて撮りました。
その思いが伝わったのか分かりませんが、その写真を見て大爆笑した患者様が笑っている姿を見ながら、生きる力になればいいなと願わずにはいられませんでした。
日本の緩和ケアは1973年の大阪の淀川キリスト教病院の「死に逝く人たちのための組織されたケア」の柏木先生をはじめとしたチーム活動が始まりでした。
柏木先生はユーモアをとても大切にしておられる方です。
著書には「ユーモアを生きる」があります。
その著書のなかに、「ユーモアは人に笑いを提供する。笑いは身体的苦痛や精神面な不安や緊張などを緩和にも大切だ」と書かれています。
また、上智大学名誉教授であるアルフォス・デーケン先生は、ドイツではユーモアの定義の一つに「愛と思いやりの現実的な表現である」とも記載されています。
写真を撮られ、それを見て笑い転げた患者様に、どうか苦痛が緩和され私の愛が届いていますように・・・
これからもユーモアで患者様に愛を伝えていきたいです。
なお、掲載されている写真は、ご家族様の許可をいただいております。